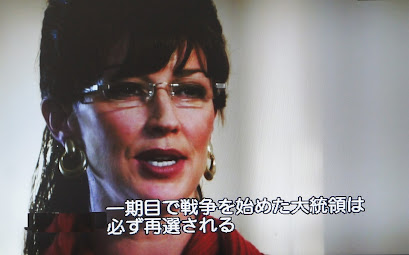Velazquez 「Kitchen Scene with Christ in the House of Martha and Mary」
ベラスケスの「マルタとマリアの家のキリスト」が、ロンドン・ナショナル・ギャラリー展に来ている(まだ見ていないが)。これは「寓意画」なので意味を読み解く必要がある。女性が料理をしているが、後ろの壁に額に入った絵が飾られている。いわゆる「画中画」だが、これは聖書の中の一節を描いたもので、キリストがマルタとマリアの家を訪れた時に、二人の姉妹がもてなすシーンだ。この絵が重要な意味を持っている。
この画中画と同じテーマをフェルメールも描いていて、こちらの方がわかりやすいので、これで説明すると、姉のマルタは料理をしてキリストをもてなす(パンを差し出している)が、妹のマリアは何もせず、キリストの足元で話を聞いている。姉は、妹も手伝うように諭して欲しいと言うが、キリストは妹の方が正しいと言う。料理でもてなすよりも、相手に心を寄せることの方が大事だと教えている。
ベラスケスの絵で、若い女性が料理をしている後ろで老女が何か話しかけているが、指は絵の方を指している。つまり絵を教訓にして、相手を思いながら心を込めて料理をしなさいと諭しているのだろう。それで若い女性は緊張して、表情がこわばっている。
手前のテーブルに魚があり、女性が作っているのが魚料理であることが重要な点だ。ギリシャ語で、「イエス、キリスト、神の、子、救い主」という言葉の頭文字をつなげると、「魚」という文字になることから、魚はキリストのアイコンとされ、古来から宗教画によく魚が登場した。ダ・ヴィンチの「最後の晩餐」のテーブルの料理も拡大すると魚料理であることが分かるという。
林 綾野という人は、キュレータで、料理研究家という人だが、名画に描かれた食べ物を実際に料理して、レシピも紹介するというユニークな取り組みをしている。今回はベラスケスのこの絵で、描かれている食材が、魚、卵、ニンニクであることから、作っているのは、スペイン料理の「魚の素揚げとアイオリソース」だろうと推定して再現している。(「美術の窓」誌 ’ 2 0 . 9 月号)