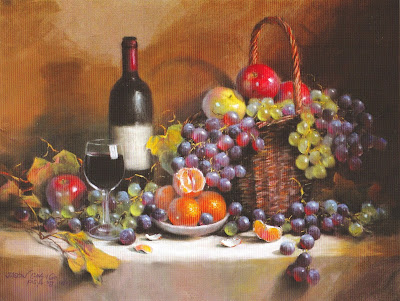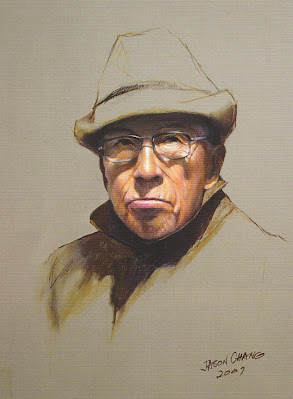Credit Title
最近ますます映画のエンドロールが長くなっているようだ。制作にちょっとでもかかわった末端の担当者たちや、端役の出演者もすべてクレジットされ、5分以上もえんえんと小さい文字がせり上がってくる。これが始まるとすぐに席を立って出ていく人もいるが、けっこう役に立つ情報が含まれていることがある。だから、動くスピードが速いが、追いついて読むようにしている。印象に残っているエンドロールをいくつかあげてみる。
日本でもヒットした「八月の鯨」は、「老い」をテーマにした映画で、人生の終わりが近い老姉妹を主人公にしたいい映画だったが、エンドロールで妹役が「Lillian Gish」と出たのでびっくり。リリアン・ギッシュはサイレント時代から大スター女優だったから、この映画に出演した時は 100 歳近かったわけだ。見ている最中は彼女がギッシュであるとは気がついていなかったが、エンドロールで知ると、なるほど美しいお年寄りなわけだと納得した。
「わたしを離さないで」は、SF 的な要素を盛り込んだ印象的な青春映画だった。エンドロールで「Based on the novel by Kazuo Ishiguro」と出た。日本人の名前なので誰だろうと思い、後で調べて、カズオ・イシグロのことを初めて知った。カズオ・イシグロがまだノーベル文学賞をもらう前のころで、映画を見るまで名前も知らなかった。
歴史的事実に基づく映画の場合、エンドロールで主人公がその後どうなったかが出ることがよくある。「イミテーション・ゲーム」は強く印象に残っている。第二次世界大戦さなか、ドイツ軍の暗号を解読して、イギリスの勝利に大貢献した天才的数学者のアラン・チューリングの物語だ。解読を人海戦術でやっているがうまくいかないなか、チューリングは解読するための機械を作って成功する。エンドロールで「この機械を今日、われわれはコンピュータと呼ぶ。」と出るのが感動的だ。またチューリングは、今でいうLGBT で、当時の法律では犯罪だったため、逮捕されてしまうのだが、これについてエンドロールで「最近エリザベス女王が、逮捕は不当であったと認め、チューリングの死後 70 年たって名誉回復がされた。」と出る。チューリングという名前自体が歴史の中で抹殺されてきたことと、その功績がやっと認められたことがわかるエンドロールだった。