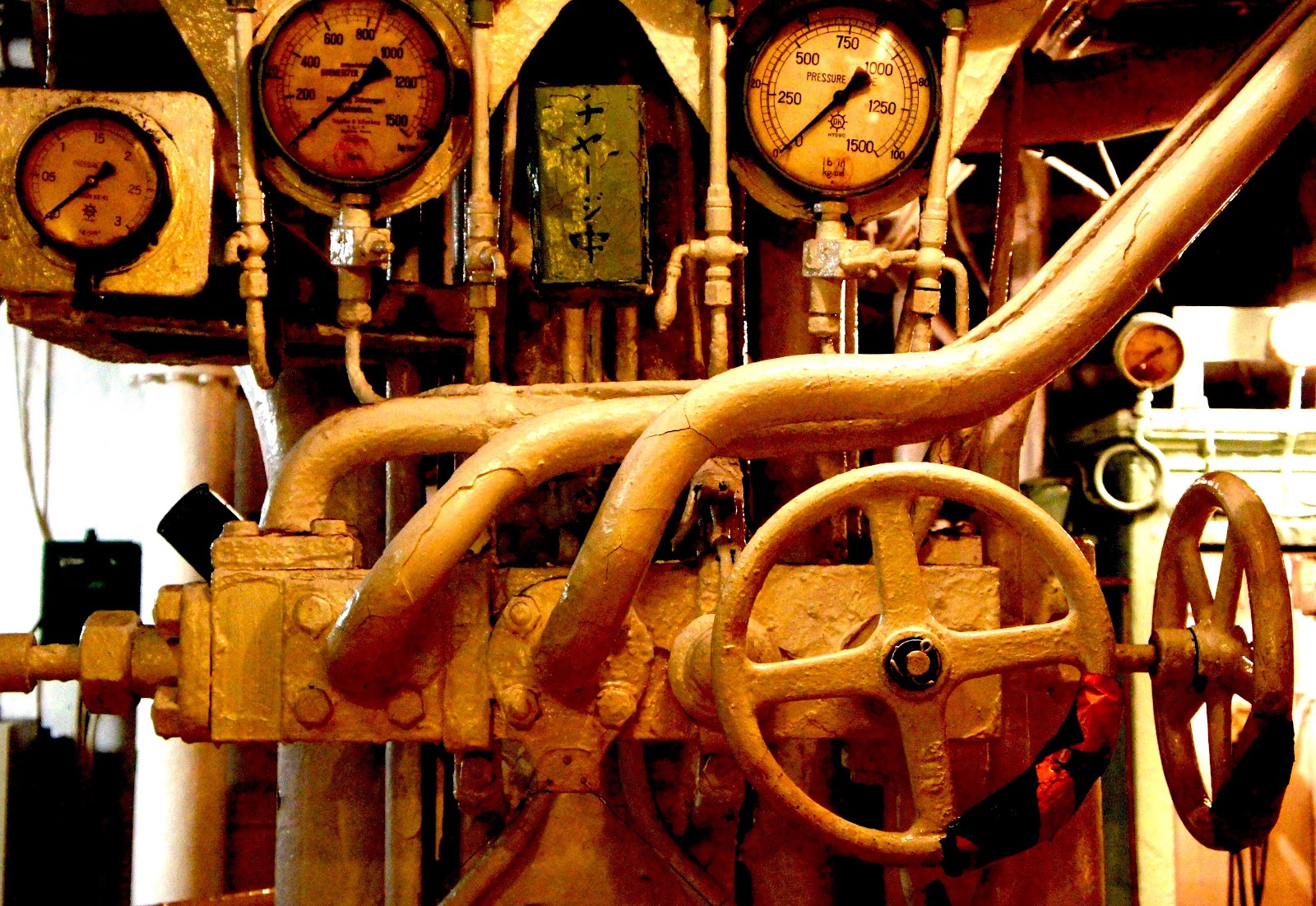American New Cinema
1970 年前後の約 10 年間、アメリカ映画に革命を起こした「アメリカン・ニュー・シネマ」は 10 年ほどであっという間に消えてしまった。それは一瞬の輝きだった。
当時のアメリカは、ベトナム戦争や公民権運動、カウンターカルチャーなど多くの社会的・政治的変動が起きていた。その格差や差別の時代に批判的で反体制的でなメッセージを込めた映画が「アメリカン・ニュー・シネマ」だった。その多くは、未来に希望を持てない若者の生き様を題材にしていた。
「真夜中のカウボーイ」は、大都会ニューヨークで失業し、しかも病気にかかってしまった若者が、暖かいフロリダを夢見て長距離バスで旅するが、到達する前にバスの中で死んでしまう。格差と貧困の社会の現実を描いていた。
「イージーライダー」は、ニューヨークで一旗揚げようとして、バイクで大陸横断をしている二人の若者が、南部に差し掛かると土地の住人に射殺されてしまう。新しい価値観を拒絶する保守的な差別社会を描いていた。
「俺たちに明日はない」は、貧しい若い男女二人組が銀行強盗をして金を稼いでいるが、最後は警官隊に包囲されて蜂の巣になって殺されてしまう。刹那的にしか生きるしかない絶望社会を象徴していた。
このような「アメリカン・ニュー・シネマ」があっという間に消えてしまったのは、当時のアメリカの政治状況の影響があった。「アメリカ映画とキリスト教」(木谷佳楠 著)という本はそのことについて明快な説明をしている。
「アメリカン・ニュー・シネマ」の全盛時代、ロナルド・レーガンがアメリカ大統領になる。レーガンはもともとハリウッドで西部劇や戦争映画のヒーロー役で人気のあった俳優だった。東西冷戦の時代だったので大統領になると、「強いアメリカ」「悪と戦うアメリカ」といった反共産主義の政策を推進し、キャッチフレーズは「Make America Grate Again」だった。(トランプ前大統領はこれをそっくり真似した)
そして反体制的な若者を共産主義者だと決めつけ、キリスト教右派と連携して、保守的な価値観を若者に強制しようとした。その影響でリベラルで反体制的な若者たちの運動は勢いをなくしていき、「アメリカン・ニュー・シネマ」も終わりになっていった。
同書はまた、「アメリカン・ニュー・シネマ」以後の映画の変化についても説明している。「ロッキー」「ランボー」「ターミネーター」などのアクション映画が人気を得るようになり、シリーズ化されていく。演じるのは、シルヴェスター・スタローンやアーノルド・シュワルツネッガーなどのアクション俳優だった。
特に興行成績のよかったのは「ロッキー4」で、ボクサーのロッキーがソ連に乗り込んでチャンピオンに挑戦し、勝利するという単純なストーリーだが、民主主義という正義を背負って戦ったヒーローの体にはアメリカの国旗が巻かれる。「強いアメリカ」を描き、その価値観を世界に押し付けるといったレーガン政権の政策を体現していた。
このような状況は、仮想敵が時代とともに変化しながらも現在にまで引き継がれてきた。ブッシュ政権下での 9.11 をきっかけにしたイスラム国への軍事侵攻や、トランプ前大統領の「アメリカ・ファースト」と称する反移民政策などが続いてきた。